期間があくを漢字で書くとどうなる?開く・空く・明くのどれが正解か
普段、何気なく使っている言葉でも、さて、これはどう書くんだろうと疑問に思ったことはありませんか?
日本語は発音が同じでも、漢字が何種類もあることは日常茶飯事です。
これまでも、いくつかの言葉について、どれが正しいんだろうということをいくつも検証してきました。
「おもう」「もとに」「かんしょう」・・・、それぞれに意味があって、それらの意味に従って漢字表記が変わってきました。
今回の対象は、「習い事をしていたのに期間があいてしまった」とか、「ずっと続けていた習慣を止めてから期間があく」などにつかう「あいて」とか「あく」に対しての漢字表記です。
いくつもの候補がありますが、どれが正しいのか見ていきましょう。
期間があくを漢字で書くとどうなる?
この場合の漢字評価は次のようになります。
期間があくを漢字で書くとどうなる?
空く
そうです。「空く」が答えなんですね。
その意味は、次の通りです!
占めていたものがなくなって、場所・時間・身体・道具などが使用できる状態になる。
「開く」「空く」「明く」を簡単に言ってしまうと次の通りです。
- 開く:開く(ひらく)
- 空く:今までそこを占めていたもの、ふさいでいたものが、除かれたり、なくなったりする
- 明く:目が見えるようになる。期間が終わる。遮っていたものがなくなる
「期間があく」に対しては、「開く」「空く」「明く」が候補に挙がりますが、その中から、上記の意味「占めていたものがなくなって、場所・時間・身体・道具などが使用できる状態になる」ということから、「空く」と書くのが正解なんですね!
「文化庁」の『「異字同訓」の漢字の使い分け例(報告)』(平成26年2月21日)の「あく・あける」には次のように載っています。
【空く・空ける】からになる。
引用 「異字同訓」の漢字の使い分け例(報告)
席が空く。空き箱。家を空ける。時間を空ける。
お上から、時間をあけるには「空ける」を使うのという「お墨付き」をいただきました。
また、「異字同訓 | 常用漢字情報サイト」でも同様の内容が載っております。
なお、yahoo!知恵袋では、この質問がいくつか出ていますが、ベストアンサーは「空く」ですね。
ベストアンサー
引用 2018/9/7 1:35
「あいた期間」を「空白期間」と言いますから、「期間があく」の「あく」は「空く(あく)」で良いと思います。
「良いと思います」の回答がベストアンサーなのが気がかりですが…。
どちらも正しいです。
引用 2018/9/7 1:35
期間と期間の間に空白があると考えるなら「期間が空く」ですし,
期間と期間の間が開いていると考えるなら「期間が開く」です。
要は,どちらのイメージを表現したいかによって,用字が変わってくるわけです。
ちょっと的外れな回答も入ってました。
「期間と期間の間に空白がある」「期間と期間の間が開いている」のイメージで字が変わると言っていますが、個人の意見ですね。
ベストアンサー
引用 2018/9/7 1:35
「あける」という漢字には、「明ける」「空ける」「開ける」がありますが、「間隔をアケる」という場合は、「空ける」がふさわしい
空くです。!!!!!
引用 2017/3/31 20:56
次に「期間が空く」を言い換えると、どんな言葉あるのか見ていきます。
※身近にある漢字をテーマにしたクイズを厳選し、楽しみながら漢字への理解を深められる内容をお届けしています。
「期間が空く」の言い換え
「期間が空く」とは、「期間が経過してしまった状態」を示します。
これを言い換えるのに便利な表現があります。
- 日が空く
- 時間が経つ
これらの言葉であれば、日常の会話やビジネスの世界でも問題なく使用できますよね!
大体、今述べた表現を使うのは、たとえば、自分が忙しくて懸案だった案件に取り掛かれなかった場合に使うことが多いですね。
- 期間が空いてしまって、ご迷惑をおかけしました
- 返信までに日が空いちゃって、すいませんでした
- やろうやろうと思っていたのに、思いのほか時間が経ってしまった
以上のような使い方をしますね。「期間が空く」「日が空く」「時間が経つ」の部分は、それぞれ別の語を当てはめても違和感はないですよね!
次に、言い換えは言い換えでも、カタカナ(英語?)でも言うことが出来ますね。それを見にいきましょう。
「期間があく」をカタカナでいうと
昔、ずっとやっていたけれども、理由があって中断していた事を久しぶりに再会する時に使うカタカナの言葉があります。
そうです。ブランクですね。
次のような使い方をします。
- 思いがけない怪我で練習ができなくなり、A選手は2年間のブランクを余儀なくされた
- 退職してブランクの空いた看護師は、復職の支援制度を利用可能である
ブランクとは、英語の blank をカタカナ表記したものなんですが、英語の blank には空白期間という意味を持たせる使い方はないんです。
そこは、豆知識として持っていましょう。
こういうとき、英語ではgapを使うようです(a gap of three years:3年間の空隙)。
他にもあります。
「スパンがあく」という表現ですね。
こちらも、「時間的な間隔があく」という意味で使うができます。
たとえば、次のように言うと、「前回から少し時間がたった・久しぶりだ」のニュアンスを出すことができますね。
- 前回から少しスパンがあいた
それでは、話を元に戻して、「開く」「空く」「明く」はどのような場合に使うのかをそれぞれ検証していきましょう。
「開く」「空く」「明く」の意味と使い方
それでは、順に「開く」「空く」「明く」の意味と使い方を見ていきましょう。
開く
「開く」は、次の場合に使用します。
- 隔てや覆いなどが取り除かれて、閉まっていたものが開いた状態になる。
- 穴などの空間ができる。
- 〔入り口の戸を開けて始めることから〕商店などの業務が始まる。また、その業務が行われる。ひらく。
それぞれの使い方を見ておきます。
- 幕が開く
- 土手っ腹に風穴が開く
- 店が開く
空く
次は、「空く」について見てみます。次の場合に使用します。
- 中身が全部使われて器がからになる。
- 占めていたものがなくなって、場所・時間・身体・道具などが使用できる状態になる。
- 欠員ができてその地位に誰も就いていない状態になる。
こちらも、それぞれの使い方を見ておきましょう。
- グラスが空く
- 午後は時間が空いている
- 委員長のポストが空く
明く
「明く」は、次の場合に使用します。
- 目が見えるようになる。
- 衣服の部分が広く開かれたりつなぎ目がなかったりして、開放された状態にある。
- 〔古い言い方で〕物忌みや契約の期間が終わる。明ける。
こちらも、それぞれの使い方を見ておきましょう。
- 目が明く
- この服は襟ぐりが明きすぎている
- 喪が明く
それぞれの使い分け
それぞれの使い分けには、次のルールがあるようです。
- 開:「閉じる・閉まる」の対語
- 空:空(から)になる、空白が生じる意
- 明:期間が終わる、明るくなって見通しが開けるなどの意
「開く」で述べた「穴などの空間ができる」は、「開放・開通する」する意の場合は「開く」を、空間ができるの意で使う場合は「空く」を使用します。
ただ、明るくなって見通しが開けるの意で、まれに「明く」も使いますが、全般にかな書きも多いのが現状です。
「一升瓶が 開く」は栓が抜かれることを、「一升瓶が空く」は瓶が空になることを示します。
それぞれの持っている意味を考慮して使用すべきですし、安易に使用すると異なった意味になってしまうので注意が必要なんですね。
また、目が見えるようになる場合には、「目が明く」というように使います。
次に、それぞれの漢字表記に着目して、その語源などを見ていきましょう。
漢字表記での違い
それぞれの漢字表記「開」「空」「明」の違いを見ていきましょう。
それぞれの漢字表記の語源と字源を見ておけば十分でしょう。
開
「開」の語源を見ていきましょう。
閉じたものを広く開けると、内部ははっきり見えて明るくなりますが、「明るい」というイメージも含まれるわけです。
そして、次のような意味も派生しました。
- 開発の開:埋もれたもの、隠れたものを明るみに出す意味
- 開化の開:滞った状態を切り開いて明るくする意味
次は、「開」の字源です。
古文の字体は「閂(かんぬき)+廾(両手)」
両手で閂をはずす情景を表します。
篆文の字体は「幵(ケン 平に揃う)+門(出入り口)」で、幵は干(棒の形)を「Hの形に揃う」イメージを示す記号です。
ここから、開は閉じてある観音開きの戸を両側に開いてそろえるイメージになります。
空
次は、「空」の語源でが、まずは、「空」のイメージから見て参ります。
- 空は、口・谷と同源で「あな」のイメージ
- 空は、工・公と同源で、「突き通る」「突き抜ける」というイメージ
空間を突き抜けると穴があくことから「突き抜ける」が空のコアイメージとなります。
そして、突き抜けた後の軌跡は何もない空間のため、「からっぽ」の意味が表れました。
突き抜けた途中は何もないから「穴」の意味を産み出しました。
何もない空間は「そら」そのものです。
一方、物事を空間化させて、ある範囲の中に何かがない(欠落している)という意味、また、中身・実質がないという意味にもなるのです。
次に、「空」の字源です。
空=「工(突き抜ける)+穴(あな)」
工は二線の間を縦の一線で突き通すことを示す象徴的符号で、「突き通す」「突き抜ける」というイメージを表す記号です。
ここから、空は穴が突き抜けているイメージとなったのです。
明
最後は「明」です。
こちらも、語源、字源で明確な違いが現れでしょうか?
語源から見て参りましょう。
暗くてはっきり見えない所をあかるくしてはっきり見えるようにすることを明という
明には「無いものを探り求める」というイメージがあり、それが、「(暗くて)わからないものをはっきりと分からせる」というイメージにつながります。
また、「明るい」は物理的イメージですが、下記のように、精神的・心理的イメージにも転用されるのです。
- 明確:事態がはっきりと見てとれる
- 解明・説明:事態をはっきり見分ける
- 賢明:道理が良くわかっている
「明」の字源ですが、「明」には明と朙の字体があります。
明=「日(太陽)+月(つき)」
明るい二つの天体を合わせて、明るさという抽象的なイメージを表します。
朙=「囧(まど)+月(つき)」
囧は明り取りの窓の形です。
そこから、朙は月の光が暗い所を照らして明るくするシーンを表しています。
このように、二つの字体がありますが、「明」は、太陽と月という明るい天体を二つ合わせて明るさを表し、朙は、月の光で明るくしており、両字体とも明るさを表現しているんですね。
最後に
期間があくといった場合に、開く、空く、明くのどれを当てると正解なのかを見てきました。
正解は「空く」でしたね。この場合は、時間があく意味となり、その意味を持っているのが「空く」だったわけです。
ただ、「あく」には色々な意味があり、その意味によってそれぞれの漢字表記が当てはまるということを明確にしました。ほんとに日本語は難しいですね!
最後に漢字表記を見てきましたが、それぞれの語源・次元により様々な意味を示していることがわかり、とても面白かったです。
参照
明鏡国語辞典
上級漢和辞典 漢字源 学研
※思えば、「ある言葉を漢字で書くと」の記事も増えてきましたよ
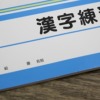









 60爺
60爺




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません