「がっこう」をローマ字で書くと?ヘボン式・訓令式でどう違うのか
日本語をローマ字で表記する際、主に「ヘボン式」と「訓令式」の2つの方法が使われます。
この2つのローマ字表記法は、それぞれ異なる特徴や歴史的背景を持っており、どちらを使用するかによって単語の見え方が変わります。
この記事では、具体的な例として「がっこう」という単語を取り上げ、ヘボン式と訓令式でどのように表記が異なるのかを詳しく解説します。
これにより、ローマ字表記に関する理解を深め、どの場面でどちらの方式を使うべきかの参考にしていただければと思います。
それでは、最後までご一緒にお付き合いください。
「がっこう」をローマ字で書くと

冒頭で述べたように、日本語をローマ字で表記する際、主に「ヘボン式」と「訓令式」の2つの方法があります。
「がっこう」のローマ字表記は、ヘボン式と訓令式のローマ字表記では次のように表記します。
- ヘボン式 gakko
- 訓令式 gakkô
上記のように少し違います。
それぞれの方式について、少し、詳しく解説しますね。
ヘボン式の「がっこう」
この方式は、日本語の発音を英語のアルファベットで表記するための標準的な方法として広く採用されています。
ヘボン式は、1873年にジェームス・カーティス・ヘボンによって考案されたローマ字表記法です。
ヘボン式ローマ字で「がっこう」を書く場合、上記の通り「gakko」と表記します。
注意すべき「つづり」のなかに、「長音は原則として記入しない」という点があります。
これ、次のような長音記号を使うのが技術的に難しい場合には、長音記号は使いません
例:Kukai(空海)
■想定される読者が日本や日本語に馴染みの薄い場合
■電子メールやインターネット上
即ち、「がっこう」の「こう」は「ko」となります。
従って、「がっこう」は「gakko」となるのです。
ヘボン式は、特にパスポートや国際的な文書で使用されることが多いです。
訓令式の「がっこう」
訓令式は、ヘボン式と並んで日本で広く使われているローマ字表記法の一つです。
特に日本国内の教育現場や公的文書で使用されることが多いです。
訓令式の特徴は、日本語の音をそのままローマ字に変換する点にあります。
そのため、日本語学習者にとっても理解しやすい表記法と言えるでしょう。
訓令式ローマ字では、「がっこう」は「gakkô」と表記されます。
「が」は「ga」、「っ」は次に続く「こ」の先頭の「k」を重ね、「こう」は長音があるので「kô」(長音は母音字の上にアクサンシルコンフレックスをつけて表わす:記事下「内閣告示第1号」参照)となります。
しょうがっこう・ちゅうがっこうのローマ字
さて、ヘボン式、訓令式の長音の理解が出来たところで、しょうがっこう(小学校)と、ちゅうがっこう(中学校)をローマ字で書いてみましょう。
既に、「がっこう」の書き方は、前章で実施していますので、「しょう」「ちゅう」の書き方に注意すればいいだけです。
| 日本語 | ヘボン式 | 訓令式 |
|---|---|---|
| しょうがっこう(小学校) | shogakko | syôgakkô |
| ちゅうがっこう(中学校) | chugakko | tyûgakkô |
おお、「がっこう」の書き方が違うだけでなく、「しょう」「ちゅう」もヘボン式と訓令式では違うのですね。
「しょう」「ちゅう」とも長音なので、「がっこう」と同様に違いが出ます。
さらに、「しょ」「ちゅ」の書き方も、ヘボン式と訓令式では違います。
実は、「しゃ」行、「tya」行の表記も全部違うんです。
| 日本語 | ヘボン式 | 訓令式 |
|---|---|---|
| しゃ | sha | sya |
| しゅ | shu | syu |
| しょ | sho | syo |
| ちゃ | cha | tya |
| ちゅ | chu | tyu |
| ちょ | cho | tyo |
このように、文字で違う表記がヘボン式と訓令式で違うモノが複数存在します。
下記のページに、その違いがあるので、気になる方は参照くださいませ。
おまけ:ヘボン式と訓令式

トレインファン, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
「HANKYU JYŪNANABAN-GAI」という間違った表記
ヘボン式ならば「JŪ」、訓令式ならば「ZYŪ」という表記になるはず
ヘボン式と訓令式の2つがあって混乱するので何とかできないのかという声は以前から言われているそうです。
英語に近いのだから、ヘボン式でいいじゃないかと思っていたんですが、・・・。
実は、世界の人口は約70億人なんですが、英語を話す人は約15~17.5億人(21.4%から25%)いますが、英語のネイティブ・スピーカーになると、わずか3.9億人(5.57%)なのです。
そう考えると、ローマ式を採用した訓令式のほうが全人類に優しい気がしてきますね。
また、訓令式は 小学生が覚えやすいようにルールを単純化した書き方だとか、今は使われなくなった古い方式だと思っている人もいますが、これも間違いです。
訓令式は、日本語の性質に合わせて設計しているため規則的ですが、ヘボン式は、そうでないため、規則性が乱れて複雑化しているのです。
なにより、訓令式はヘボン式より後に作られた新しい方式なのです。
60爺も、「今は使われなくなった古い方式」だと考えていたんですが、訓令式の方が新しいとは「目から鱗が落ちる」って奴ですな!
確かに、訓令式は 日本語の 性質に あわせて 設計 して あるから 規則的です。
日本語を大事にするということからいえば、訓令式に舵を切るのもいいかもしれませんね。
でもかんでも英語に近いモノにすれば良いと考えるのは日本人位なのかも。
訓令式の方が日本語に近いので大切にすべきかと考えさせられます。
なお、2025/06/20文化庁は、ローマ字の統一的な表記として、英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする答申素案をまとめました。
これにより、ローマ字表記は「訓令式」を基本とした1954年の内閣告示は、約70年ぶりに変更されます。
変更例をいくつかしまします。
| 日本語 | ヘボン式 | 訓令式 |
|---|---|---|
| し | shi | si |
| ふ | fu | hu |
| じゃ | ja | jya |
| ちゅ | chu | tyu |
ただし、統一的な表記を重視するがあるものの、「個人や団体などにおいて、長年用いられてきたつづり方は尊重し、直ちに変更を求めるものではない」ことも明記するそうです。
何とも、曖昧模糊な、日本人的な発想ですな!
※「雑談の部屋」の次の記事です。
※「雑談の部屋」の一つ前の記事です。
最後に
「がっこう」をローマ字で書くとどうなるのか、日本で使われるヘボン式・訓令式でどう違うのかをみてきました。
長音に関してヘボン式・訓令式には違いがあり、その表記が違うことが分かりました。
合わせて、しょうがっこう、ちゅうがっこうをローマ字で書いて見て、さらにその違いが顕著であるとわかりました。
中々、難しいモノがありますが、ヘボン式・訓令式をどうするか検討すべきなのではないでしょうか。
参考
ヘボン式を基本とした推奨形式|日本語のローマ字表記の推奨形式
ヘボン式と訓令式? ローマ字の混乱しない学び方とは
訓令式 ローマ字について
内閣告示第1号そえがき|ローマ字のつづり方|文化庁
※「雑談の部屋」の記事はすごい大所帯です!








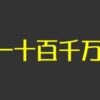


 60爺
60爺




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません