クジラは何類に分類される?その理由を特徴とともに詳しくご紹介
クジラは海を泳ぐ巨大な生き物で、その姿は魚とよく似ています。
水中を自由に泳ぎ、ヒレを持ち、エラのような構造が見られることから、「クジラは魚類なのでは?」と考える方も多いでしょう。
しかし、クジラの分類については、特徴を詳しく見ていくと、意外な事実が浮かび上がります。
生物の分類は、外見だけで決まるわけではなく、骨格の構造や呼吸の仕方、繁殖方法など、さまざまな要素が関係しています。
クジラがどのように分類されるのかを知るためには、その生態や進化の過程に注目する必要があります。
本記事では、クジラが何類に分類されるのかを、特徴や身体のつくり、そして進化の痕跡とともに詳しく紹介します。
どうか最後までご一緒にお付き合いください。
クジラの分類とは?

The original uploader was Zorankovacevic at English Wikipedia., CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
始めに、クジラが何類なのか見ておきましょう。
クジラは、見た目は魚のようですが、実際には哺乳類に分類されます。
クジラは哺乳類に分類される海の生き物なんです。
見た目は魚類に似ていますが、肺で呼吸し、子を産んで母乳で育てるなど、哺乳類の特徴を持っています。
進化の過程をたどると、クジラの祖先は陸上で暮らしていた哺乳類であり、水中生活に適応する中で現在の姿へと変化しました。
また、クジラは「ハクジラ類」と「ヒゲクジラ類」の2つに分類され、歯の有無や食べ方が異なります。
こうした分類を知ることで、クジラの生態への理解が深まるでしょう。
哺乳類は、肺で呼吸を行い、自身で体温を調整する恒温動物で、胎生(受精卵が母体内で発生し、ある程度発育してから産み出される)特徴を持つ動物です。
哺乳類としてのクジラの特徴
クジラが哺乳類であるという特徴を以下に示します。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 呼吸 | クジラは、鼻孔(噴気孔)を持っており、肺で空気呼吸をします。 これは、陸生哺乳類と同じです。 |
| 体温 | クジラの体温は(種類により違いますが)概ね35℃~36℃と一定しており、恒温動物と言われる由縁です。 この点は、ほとんどの魚類が外海の温度に左右されることと異なっています。 |
| 産まれ方 | クジラの場合、胎生であるため、一子が母体子宮内で成長し出産します。 その大きさは、母体の1/2から1/3に達するほど大きいです。 |
「クジラの潮吹き」は有名ですが、この潮吹きこそがクジラの呼吸で「噴気」と呼ばれています。
クジラが寒冷な海域でも体温を維持できるのは、分厚い脂肪層(ブリーバー)があるためです。
この脂肪層は断熱効果を持ち、体温の低下を防ぎます。
クジラの子どもが大きいのは、(冷たい水の中でも)自力で体温を保てるようにするためです。
また、クジラ類は、水中で暮らすようになったことで、骨盤をなくし、産道が大きく広がるようになったことで、大きな子どもを産めるようになりました。
※動物の分類についてまとめた記事に、この内容を紹介しています。
※哺乳類に属する動物の記事は次の通りです。
クジラの特徴と生態

The original uploader was Zorankovacevic at English Wikipedia., CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
クジラの特徴と生態をまとめましたので、ご確認ください。
| クジラの特徴 | 概要 |
|---|---|
| 巨大な身体 | シロナガスクジラは地球最大の動物(体長30m以上)。 |
| 噴気孔 | 頭の上にあり、呼吸時に水蒸気を吹き出す。 |
| 高い知能 | 複雑なコミュニケーション能力を持ち、群れ(ポッド)で協力する。 |
| 進化の痕跡 | 前肢は胸びれとして機能し、後肢は退化して体内に痕跡が残る。 |
| エコシステムの重要な一部 | 海洋環境に影響を与え、排泄物がプランクトンの成長を促す役割を持つ。 |
順番に、それぞれの内容を見ていきます。
巨大な身体
クジラは地球上で最も大きな動物の一つで、特に、シロナガスクジラは最大の生物として知られています。
その体長は30メートル以上に達し、体重は150トンを超えることもあります。
大きな体は捕食者から身を守るのに役立ち、寒冷な海域でも体温を維持しやすいという利点があります。
また、巨大な肺を持ち、一度の呼吸で長時間潜水できるのも特徴の一つです。
噴気孔
前章で少し触れましたが、クジラの噴気孔は頭の上にあり、呼吸のために水面へ浮上すると勢いよく空気を吹き出します。
ヒゲクジラは2つ、ハクジラは1つの噴気孔を持ちます。
吐き出されるのは水ではなく、温かい呼気が冷たい外気と触れて水蒸気となるため、水柱のように見えます。
噴気の形状は種類によって異なり、クジラの識別にも利用されます。
また、噴気孔には弁があり、潜水中に水が入らない仕組みになっています。
※ハクジラの中に、幻のクジラと呼ばれるバハモンドオウギハクジラがいます。そのクジラを追いかけた記事がこちらです。
高い知能
クジラは非常に高い知能を持つ動物で、複雑な社会構造や高度なコミュニケーション能力を持っています。
特に、ハクジラ類のイルカやシャチは、音を使ったエコーロケーションで周囲を認識し、仲間と連携して狩りを行います。
ザトウクジラは独特な歌を歌い、個体ごとに異なるパターンを持つことが確認されています。
また、学習能力や記憶力が高く、道具を使ったり遊びをしたりする行動も観察されています。
進化の痕跡
クジラの前肢は「胸びれ」と呼ばれ、泳ぐ際の方向転換やバランスを取る役割を果たします。
この胸びれの内部には、陸上哺乳類と同様の骨格構造(上腕骨・橈骨・尺骨・指骨)が残っています。
一方、クジラの後肢は進化の過程で退化し、外見上は存在しませんが、体内にはわずかな痕跡が残っています。
これは、クジラがかつて陸上で生活していた祖先を持つことを示す証拠とされています。
このような特徴は、クジラの進化を理解する上で重要なポイントです。
エコシステムの重要な一部
クジラは海洋エコシステムにおいて重要な役割を担っています。
まず、彼らの排泄物は鉄や窒素などの栄養素を含み、植物プランクトンの成長を促進します。
これにより、海洋の炭素循環が活性化され、気候変動の抑制にも貢献しています。
また、クジラの死骸は海底に沈み、「ホエールフォール」として多くの深海生物の貴重な栄養源になります。
こうした働きにより、クジラは海洋全体の生態系のバランスを維持する重要な存在となっています。
生息環境
クジラは世界中の海に生息しており、種類によって適応する環境が異なります。
シロナガスクジラやナガスクジラなどのヒゲクジラは主に冷たい海域を回遊しながらプランクトンを捕食します。
一方、マッコウクジラやシャチなどのハクジラは温暖な海域から深海まで幅広く分布し、魚やイカを捕食します。
また、一部の種類は季節ごとに繁殖や採餌のために長距離を移動することが知られています。
最後に
クジラはその見た目から魚類と誤解されがちですが、生物の分類は外見だけで決まるものではありません。
本文で明らかにしたように、クジラは哺乳類でした。
水中で生活するために特殊な特徴を持つクジラですが、その祖先は陸上で暮らしていました。長い進化の過程を経て、現在のような姿になったのです。
呼吸の仕方や子育ての方法など、クジラには独自の生態があり、これが分類の決め手にもなっています。
本記事を通じて、クジラの分類に関する正しい知識を深めることができたのではないでしょうか?
クジラの生態を理解することで、海の生き物に対する見方も変わるかもしれません。
■追記:何類をテーマに記事をいくつか書いています






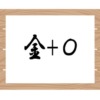










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません