羊羹の数え方は?余り聞かないモノから聞きなれたモノまで全部ご紹介
羊羹といえば、日本の伝統的な和菓子のひとつ。
お土産やお茶うけとして親しまれていますが、実はその数え方にはさまざまなバリエーションがあることをご存じでしょうか?
現在では、よく聞く「○本」と数えることが多いようですが、形状や提供方法によっては「個」や「切れ」など、異なる数え方も使われます。
しかし、羊羹の数え方には独自の表現があることをご存知でしょうか。
この記事では、羊羹の数え方について、あまり知られていないものから、現在、幅広く使用されている定番まで、幅広くご紹介します。
数え方を知ることで、より深く羊羹を楽しむきっかけになるかもしれません。さっそく、その世界を覗いてみましょう!
それでは、ご一緒に最後までお付き合いください。
羊羹の基本的な数え方
羊羹を数えるときの単位は複数あります。
それらの単位を以下に示します。
| 数え方 | 読み |
|---|---|
| 本 | ほん |
| 切れ | きれ |
| 個 | こ |
| 棹 | さお |
| 折 | おり |
| 箱 | はこ |
おお、6つの数え方が出てきました。
皆さん、これらの数え方を知っていましたか?
中には見慣れない数え方もありますね。順にみていきましょう。
本(ほん)
現代では、最も一般的に使われるのは「本(ほん)」だと思います。
棒状の羊羹を1本、2本と数えるのが一般的で、これは店頭で販売される箱入りの羊羹や、贈答用の羊羹にも適用されます。
たとえば、「虎屋の羊羹を1本買った」「3本入りのセットを贈る」といった使い方をすることが多いでしょう。
切れ(きれ)

また、羊羹を切り分けて提供する場合には「切れ(きれ)」が使われます。
家庭や茶席などで、羊羹を小さく切ってお皿に盛る際には、「羊羹を3切れ取り分ける」といった表現が適切です。
特に一口サイズにカットされた羊羹を数えるときに便利な数え方です。
個(こ)

一方で、小分け包装された羊羹やミニサイズの羊羹は「個(こ)」で数えられます。
例えば、コンビニやお土産売り場で見かける個包装の羊羹は、「1個」「2個」と数えるのが自然です。
特に登山やアウトドアで携帯しやすい一口サイズの羊羹は「1個食べる」といった言い方が一般的です。
これらの数え方を理解しておくと、羊羹を買うときや贈るとき、あるいは食べるときにも適切な表現ができるようになります。
基本的には、羊羹の形状や状態に応じて「本」「切れ」「個」を使い分けるとよいでしょう。
次に見ていただくのは、あまり聞かない羊羹の数え方です。
羊羹の数え方として「本」「切れ」「個」が現実的ですが、実はあまり聞かない、やや専門的な数え方も存在します。
その中でも「棹(さお)」「折(おり)」「箱(はこ)」という3つの数え方は、特定の場面で使われることが多く、羊羹に対する理解を深めるのに役立ちます。
棹(さお)

「棹(さお)」は、羊羹がまだカットされていない状態、つまり一本そのままの姿を指す数え方です。
これは、昔からの言い方で、「棹物(さおもの)」という言葉もあるように、羊羹だけでなく、同じ形状(細長く棒状)の和菓子に適用されます。
この棹物(さおもの)ですが、「棹菓子(さおがし)」や「棹物菓子」とも言われます。
棹菓子は格の高い菓子とされて、主に、贈答に用いられていたようです。
そして、「この羊羹は1棹で販売されています」といった形で使われます。
一般的な「本」と似ていますが、より伝統的な表現といえるでしょう。
折(おり)
「折(おり)」は、羊羹が特定の容器や木箱に詰められた状態を指す数え方です。
「折詰(おりづめ)」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは和菓子やお弁当を詰めた容器のことを意味します。
小売で販売される際に、折詰に入れられた羊羹を「1折」「2折」と「折」で数えます。
茶席や贈答用の高級羊羹に見られる表現で、百貨店や和菓子の老舗で目にすることがあるかもしれません。
箱(はこ)
「箱(はこ)」は、羊羹が複数本セットになった状態で販売されている場合の数え方です。
こちらも、「折」と同様に、小売で販売される際に使う数え方です。
贈答品や詰め合わせの羊羹は、1本単位で数えるのではなく「1箱」「2箱」と数えます。
例えば、「この羊羹は3本入りの箱で販売されています」といった使い方が一般的です。
特に、お歳暮やお中元などのギフト商品では、「箱」で数える場合があります。
数え方「棹」の雑学
「棹」と言う数え方がありました。
この数え方は、上述したように、「羊羹」や「ういろう」など細長い棒状の和菓子である「棹物(さおもの)」に適用されるモノです。
「棹」を使う理由は、羊羹などを流しこんで固める型箱が「船」と呼ばれたためです。
船には「さお」が付き物であることから、羊羹も「一棹、二棹」と数えるようになったそうです。
箪笥の数え方も「棹」

この「棹」は、タンスを数える場合にも用いられます。
昔のタンスは現在よりも小ぶりで、上部に金具がついており、火事などがあると、ここに竹竿を通して運び出しました。
タンスの数と運び出すための「さお」の数が一緒だったので、タンスの数え方が「棹」になったんですって。
三味線の数え方も「棹」

他に三味線も「棹」で数えます。
三味線の柄が細長いことから、「棹」を使うようになりました。
物の数え方を一覧にしています。
⇒ 物の数え方を一覧にした!面白い助数詞をたくさん知って博識になろう
最後に
羊羹は、日本の伝統的な和菓子でありながら、その数え方には意外なバリエーションがあります。
一般的な「本」「切れ」「個」だけでなく、「棹」「折」「箱」など、販売形態や文化によって異なる数え方が使われます。
「棹」は昔から使われる伝統的な数え方で、棹菓子と呼ばれる和菓子の数え方でした。
この「棹」、羊羹だけではなく、タンスや三味線にも用いられるんです。
※思えば、「数え方」の記事も増えてきています。




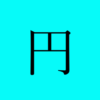











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません