四六時中とは何か?その読み方から意味・昔の言い方まで総特集
「四六時中」という言葉は、日常会話の中でも、よく見かける表現の一つです。
「四六時中気にしている」「四六時中働いている」などのように使われ、何かを常に行っている様子を表します。
しかし、なぜ「四六時中」と言うのでしょうか?
この表現の由来をたどると、江戸時代の時間の概念にまで遡ることができます。
この表現について、昔はどのような言い方があったのか、同じ意味を持つ類語にはどんなものがあるのかも気になるところです。
本記事では、「四六時中」の読み方や意味、語源から、かつて使われていた別の表現、さらに現代での使い方までを詳しく紹介します。
この機会に、普段何気なく使っている言葉の背景を知り、より深く日本語を理解してみましょう。
四六時中の読み方と意味
「四六時中」は、割と見かける言葉の一つです。
始めに、この言葉の読み方を確認してから、その意味と使い方を紹介します。
「四六時中」の読み方
「四六時中」は「しろくじちゅう」と読みます。
この読み方は、現代の日本語において広く定着しており、口語でも文語でも自然に使われています。
この読み方を、時折「しむつじちゅう」と読んだり、「しろくじなか」といった誤用をする人がいないとも限りません。
正しくは「しろくじちゅう」ですので、覚えちゃいましょう。
※漢字自体は簡単でも読み方の難しい漢字は多々あります。「四六時中」は番外編で収録です。
「四六時中」の意味
「四六時中」は、何かがずっと続いていることを表します。
即ち、「いつも」とか「しょっちゅう」と言う意味になります。
なぜ、こう言う意味になるかといえば、九九に辿り着きます。
「しろく」は九九で答えを出すと24になります。
「しろくじちゅう」=「24時間中」となるので、イコール一日中となる訳です。
ここから、上述の意味「いつも」「しょっちゅう」になるのです。
「四六時中」の使い方
上述したように、「四六時中」は、時間の長さに関係なく「ずっと続いている」ことを強調する表現です。
この言葉は、良いことにも悪いことにも使うことができます。
例をいくつかみていきましょう。
ポジティブな例
- 「彼女は四六時中笑顔で、周囲を明るくしてくれる」(常に笑顔でいることを表す)
- 「子どもが生まれてから、四六時中幸せを感じている」(絶え間なく幸せを感じていることを表す)
ネガティブな例
- 「彼は四六時中文句ばかり言っている」(ずっと文句を言っていることを表す)
- 「四六時中スマホをいじっていて、勉強に集中できない」(一日中スマホを触っていることを表す)
ご覧のように、日常会話でも使うことが可能ですので自然に活用してみましょう。
四六時中の語源と由来
「四六時中(しろくじちゅう)」という言葉の語源を追っていくと、同じ意味でよく似た「二六時中(にろくじちゅう)」という言葉に行き当たります。
goo辞書の「二六時中の解説」では次の内容が載っています。
《昔、1日が12刻であったところから》終日。一日中。また、いつも。
二六時中の解説 – 小学館 デジタル大辞泉|goo辞書
この「二六時中」ですが江戸時代の時刻制度に由来しています。
即ち、江戸時代の時刻は、一日の時間を大きく二つに分け、それらを六つに分け(1日が12刻)て時刻を表していました。
そこから、「にろく」(=12)という言葉が生まれ、「二六時中」=「一日中」という意味になったのです。
夏目漱石の小説にも、「二六時中」が使われています。
電車が通るようになれば自然町並も変るし、その上に市区改正もあるし、東京が凝としている時は、まあ二六時中一分もないといっていいくらいです
しろくじちゅう|こころ/夏目漱石
このように、かつては「二六時中」という言い方がされていました。
時刻制度が変わったことで、「二六」を「しろく」に置き換えて、「四六時中」という言葉が伝わってきたのです。
「四六時中」の類語
「四六時中(しろくじちゅう)」という言葉は、上述の通り、「常に」「一日中」といった意味で使われていますが、この章では、言い換え表現について紹介します。
次のような表現があります。
- 終始(しゅうし)
- 絶えず(たえず)
- 年がら年中(ねんがらねんじゅう)
- いつも
これらの言葉は、それぞれ微妙に異なるニュアンスを持っています。
場面に応じて使い分けることで、より適切な表現ができるようになるでしょう。
終始(しゅうし)
物事の始まりから終わりまで続いていることを表します。
「終始一貫」のように、物事がぶれずに続く意味でも使われます。
*例:「彼は終始冷静だった。」(最初から最後まで冷静だった)
絶えず(たえず)
何かが途切れることなく続いている様子を表します。
「四六時中」とほぼ同じ意味ですが、よりフォーマルな印象を与えます。
*例:「川の水は絶えず流れている。」(ずっと流れ続けている)
年がら年中(ねんがらねんじゅう)
一年を通して、ずっと続いていることを意味します。
「四六時中」が一日の範囲で使われるのに対し、「年がら年中」は長い期間を指します。
*例:「彼は年がら年中旅行している。」(一年中、いつも旅行している)
いつも
最もシンプルな言い換え表現。
「四六時中」ほどの強調はなく、日常的な頻度を表す際に使われます。
*例:「彼はいつも元気だ。」(普段から元気である)
最後に
四六時中は「しろくじちゅう」と読み、「常に」「一日中」といった意味を持ち、割と目にする表現です。
この言葉は、江戸時代の時刻制度に由来し、昔は「二六時中」と言われていました。
現代では、24時間制となったため、「二六」が「四六」となって定着しました。
普段何気なく使う言葉にも、歴史や文化が深く関わっています。
これを機に、日本語の背景を知り、より豊かな表現力を身につけてみてはいかがでしょうか。
※気づけば言い方・呼び方の漢字の記事も増えてきました

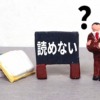














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません