部首「れんが」とは何か?その意味からどんな形・由来までを総特集
日本語の漢字には、それぞれの成り立ちや意味を担う「部首」という重要な要素があります。
その中でも、「れんが」という部首を聞いたことがありますか?
部首「れんが」は、形を示されれば「これがそうなのか」と誰でも知っているものですが、名前や由来、意味については余り知られていないと思います。
「れんが」とは一体どんな部首なのか?なぜこの名前がついたのか?どんな漢字に使われているのか?
今回の記事では、「れんが」という部首にスポットを当て、その意味や形の特徴、そして成り立ちの背景に迫っていきます。
知れば知るほど奥深い漢字の世界。
どうか最後まで、ご一緒にご覧になってください。
部首「れんが」とは
最初に部首「れんが」をご覧になってください。
灬
これが部首「れんが」です。
これをみれば、「これがそうだったのか」と、皆さんご存知の形だと思います。
普段は漢字をみても、部首の名前までは覚えようとはしないですからね。
この部首は、「れんが」の他にも、「れっか」「れんか」「よつてん」「よってん」という呼び名があります。
「れんか」「連歌」は「連火」、「れっか」は「列火」と書きます。
「灬」部には「灬」を含む漢字や、「火」の状態・作用に関する漢字が集められています。
実は、この「灬」、火の変形なんです。
「火」が「脚(あし)」になると、この形になるのです!
ですから、本来は、「火」と同一の部首なんですが、形が異なるため、漢字源では別部首としています。
漢字の部首は、次の7種類に分類されます。
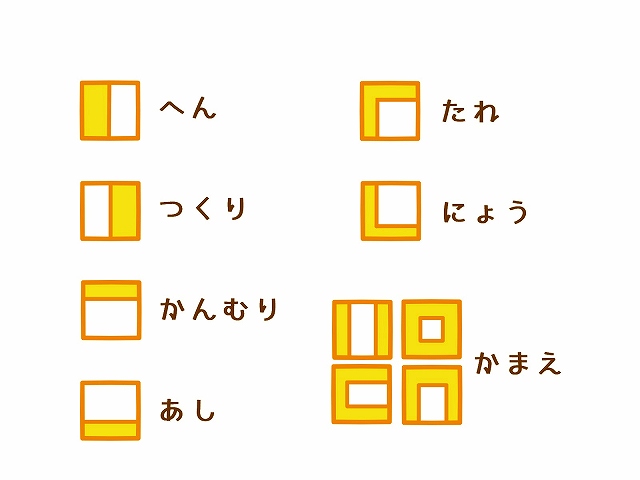
ご覧のように、位置する場所によって、へん(偏)、つくり(旁)、かんむり(冠)、あし(脚)、たれ(垂)、にょう(繞)、かまえ(構)と呼ばれるのです。
「れんが」の由来
「れんが」は上述したように、火が脚にあるスタイルで、炎が地面に広がる様子を表しているとされます。
篆分の「火」の形が次第に崩れていき、隷文で「れんが」の形に近づき、現代の形になっていく流れは、次のサイトに出ています。
ただ、この記事でも言っているように、「篆文の成立年代がはっきりわからず、この流れは推定にすぎない」そうです。
白川フォントで「熊」を入力して、篆文の「熊」を検索しました。

「れんが」を含む漢字、例えば「熱」「燃」「然」などは、いずれも火や熱、変化を示す意味を内包しています。
「れんが」は単なる形の部品ではなく、漢字全体の意味に深く関わっているのです。
※部首で書いた記事は次の通りです。
部首「れんが」の漢字一覧
部首「れんが」の漢字を一覧にしました。
| 漢字 | 画 数 | 常用/人名用/1/2 | 音読み | 訓読み |
|---|---|---|---|---|
| 点 | 9画 | 常用 | テン | つけ・る、とぼ・る、とも・る、たてる |
| 為 | 9画 | 常用 | イ | ため、す・る、な・す、つく・、おさ・める |
| 烈 | 10画 | 常用 | レツ | はげ・しい |
| 烏 | 10画 | 人名用 | ウ、オ | からす、くろ・い、いずく・んぞ、なん・ぞ |
| 烹 | 11画 | 1 | ホウ | に・る |
| 烋 | 11画 | 2 | キュウ、コウ | さいわ・い |
| 烝 | 11画 | 2 | ジョウ、ショウ | む・す、すす・める、もろもろ、まつり |
| 然 | 12画 | 常用 | ゼン、ネン | も・える、しか・り |
| 無 | 12画 | 常用 | ム、ブ | な・い、なみ・する |
| 焦 | 12画 | 常用 | ショウ | こげ・る、あせ・る、じ・らす |
| 煮 | 12画 | 常用 | シャ | に・る |
| 焉 | 12画 | 2 | エン | いずく・んぞ、ここ・に、これ |
| 照 | 13画 | 常用 | ショウ | て・る |
| 煎 | 13画 | 常用 | セン | い・る、に・る |
| 熊 | 14画 | 常用 | ユウ | くま |
| 煦 | 14画 | 2 | ク | あたた・める、めぐ・む |
| 熱 | 15画 | 常用 | ネツ | あつ・い、ほて・る、いき・る、ほとぼり |
| 熟 | 15画 | 常用 | ジュク | う・れる、に・る、こな・す、な・れる、こな・れる、つらつら、つくづく |
| 熙 | 15画 | 人名用 | キ | ひか・る、ひろ・い、よろ・こぶ、たの・しむ、やわ・らぐ、ああ |
| 煕 | 15画 | 2 | キ | ひか・る、ひろ・い、よろ・こぶ、たの・しむ、やわ・らぐ、ああ |
| 燕 | 16画 | 人名用 | エン | つばめ、さかもり、くつろぐ |
| 熬 | 16画 | 2 | ゴウ | いる |
| 熈 | 16画 | 2 | キ | ひか・る、ひろ・い、よろ・こぶ、たの・しむ、やわ・らぐ、ああ |
| 熹 | 17画 | 2 | キ | あぶ・る、さか・ん、よろこ・ぶ |
常用漢字、人名用漢字、JIS第一水準、第二水準までの漢字です。
今回、環境依存文字は、上記の範囲に入っていても除いています。
次に、これらの漢字の字源を挙げます。
| 漢字 | 字源 |
|---|---|
| 点 | 一つの場所に定着した(くっついて離れない)黒いしみ |
| 為 | 自然の物に人工を加えて姿や性質を別の物に変えることを暗示 |
| 烈 | 火が燃えて炎が四方に分散する情景 |
| 烏 | 鳥の目を表す「一」を省いた図形 |
| 烹 | 火で煮て、湯気が上下に通い、芯まで通ること |
| 烋 | 外からかばって暖めること |
| 烝 | 火気が高い所へ上がること |
| 然 | モノを燃やして柔らかくすることを示す |
| 無 | 舞い踊って隠れて見えないものを求める状況 |
| 焦 | 小鳥を火であぶって焼く情景 |
| 煮 | 火を燃やして熱を集中させる状況 |
| 焉 | エンという鳥を描いた字 |
| 照 | 火の光で明るく照らす情景 |
| 煎 | 火の熱を平均して揃え、むらなく通して熱する状況 |
| 熊 | 火のように勢いがあり力強い動物、クマを暗示させる図形 |
| 煦 | 中に包んで暖めること |
| 熱 | 火が燃えるときに出る気(熱気)を暗示させる図形 |
| 熟 | 火をむらなく良く通して煮る状況 |
| 熙 | 火の光が上がって丸く広がる状況 |
| 煕 | 熙の異体字 |
| 燕 | ツバメの全形を描いた図形。下部は二つに分かれた尾の形で火ではない |
| 熬 | 遠慮会釈もなく強い火でいりつけること |
| 熈 | 熙の異体字 |
| 熹 | ふうふうと立ち上る熱気で煮炊きすること |
この部首の常用漢字は12ありました。
いずれも、皆さんのなじみの深い漢字が多いでしょう。
字源を見ていくと、「点」「為」「烏」「無」「焉」の5つが、直接、火とはかかわりのない漢字ですね。
ただ、「烏」は意味の中に「中国では、太陽の中に三本足のカラスがいるという伝説があった」そうで、「火」と関わりがありそうです。
「熊」は人関係ないだろうと思ったのですが、「火のように勢いがあり力強い動物」とは恐れ入りました。
「れんが」の出し方
この部首「れんが」ですが、パソコン・スマホ・テプラで出せるのでしょうか。
結論から申しますと、パソコンとスマホではだせますが、テプラ(TEPRA PRO SR300)では出せないようです。
パソコン及びスマホについて、その出し方を紹介します。
「れんが」の出し方(パソコン)
パソコンでは文字変換かUnicode入力、IMEパッドによる手書き入力の3つの方法が使えます。
文字変換
「か」を入力します。
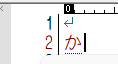
変換キーを何度も押します。次の画面になるまで押してください。
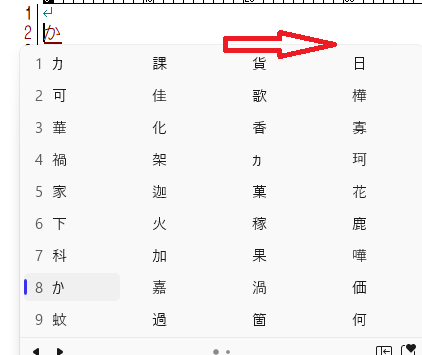
「→」キーを「単漢字」が出るまで押します。次に、単漢字をクリックします。
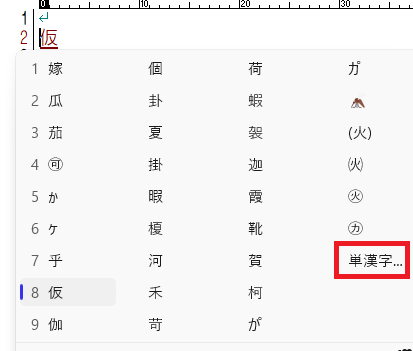
「→」キーを「灬」が出るまで押します。「灬」を見つけたらクリックします。
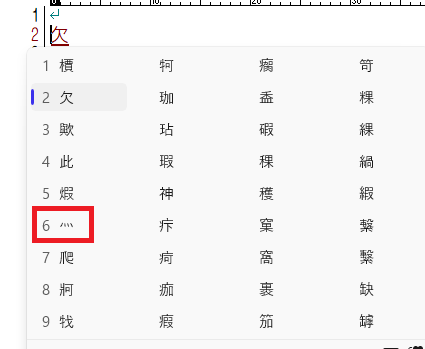
「灬」が入力できました。
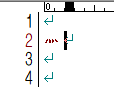
Unicode入力
日本語で「706C」と入力します。
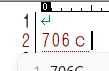
F5キーを押します。候補が出るので、「れんが」を選択します。
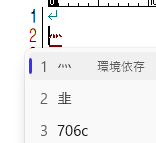
「灬」が入力できました。
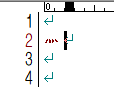
IMEパッドによる手書き入力
入力する先を用意します。60爺は「秀丸」ですが、メモ帳でも何でも構いません。
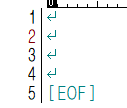
IMEパッドを出しましょう。
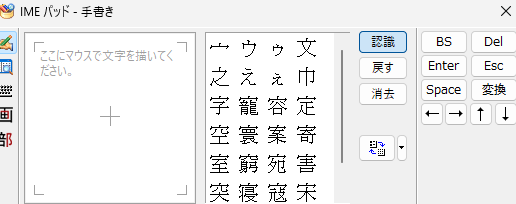
出し方をご存知ない方は、こちらの記事を参照ください。
マウスを使って「れんが」(赤枠)を書きます。候補の中に「れんが」が出ます(赤矢印)のでクリックします。
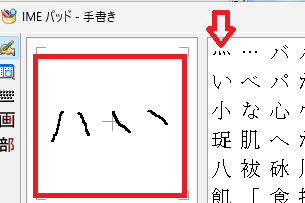
「灬」が入力できました。
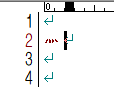
パソコンではUnicodeを知っていれば、それが一番早いのですが、覚えていられないので、手書き入力がいいかと思います。
文字変換は、候補が多くて「灬」を探すのが大変なので…・・・。
「れんが」の出し方(スマホ)
今度は、スマホでの「れんが」の出し方です。
「れんが」と入力します。
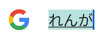
androidのスマホであれば、変換候補に「灬」が表れると思います。タップします。
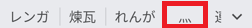
パソコンよりも簡単に「灬」を出せました。

パソコンでは、「か」を入れて変換キーを押してから、物凄いたくさんの変換候補が出ましたが、スマホでは「れんが」入力ですぐに「灬}を見つけることが出来ました。
最後に
「れんが」という変わった部首は「れんが」という形です。
この形をみれば、「これがそうだったのか」と誰もがうなずく部首ですよね。
これが、火の変形である部首だとは知ってビックリ、思いもよらぬものではなかったでしょうか?
今回は、この「れんが」について、なぜこの名前がついたのか?どんな漢字に使われているのかを紹介しました。
※思えば、「漢字の旧字」の記事も増えてきたようです。
参考
上級漢和辞典 漢字源










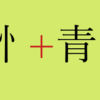




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません